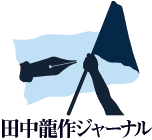マイティガ空軍基地。2月、内戦が始まるとアフリカ諸国から連日、傭兵が運びこまれた。(トリポリ。写真:筆者撮影)
首都トリポリの東端にあるマイティガ空軍基地は王政時代、米軍が使用していた。カダフィ政権となって(1969年~)からはソ連やアルジェリアをはじめとするアフリカ諸国の軍用機が頻繁に飛来するようになった。独裁者が「打倒欧米」を激しく叫んでいたためNATO軍機の利用は当然ない。
2月、反政府軍が蜂起し事実上の内戦状態となるとマイティガ基地は“本領”を発揮し始める。政府軍の空軍大佐から反政府軍に重要な情報がもたらされた――
アルジェリアはじめアフリカ諸国から傭兵を積んだイリューシン(ソ連製輸送機)が連日、マイティガ基地に降り立っているというのだ。
反政府軍に緊張が走った。自国民からなる軍隊であれば、国民に銃を向け国土を破壊するのは嫌気がさす。厭戦気分の蔓延につながる。だがカダフィが金で雇った傭兵はそんなことお構いなしだ。傭兵たちはリビアの国民に銃弾を浴びせ国土を爆撃した。戦闘は半年も続き多くのリビア国民が死傷することになったのである。
反政府軍に第一級のインテリジェンスを伝えたのは、ファラジ空軍大佐(50歳)だった。同大佐に会い話を聞いた。「カダフィは正規軍を嫌っていたからね。やりづらかったよ。カダフィは傭兵と親衛隊しか大事にしなかった」。ファラジ大佐は当時を振り返った。
カダフィは、自らの出身部族と違いトリポリへの対抗意識が強い東のベンガジを目の敵にした。カダフィにベンガジ空爆を命じられたため反政府軍に駆け込んだ将校がいた。アリ・ハドゥス大尉だ。大尉は内戦が始まるとすぐにミスラータに拠点を構える反政府軍に合流した。
操縦桿を銃に持ち替えてカダフィの軍隊と戦ったが、戦闘開始から50日を過ぎた頃、被弾し命を落とした。
前出のファラジ大佐に新国家の軍隊はどうあるべきかを聞いた。「(傭兵のように金で動くのではない)誠実な人間が求められる。体制のためでなく、人々のための、神のための軍隊であるべきだ」。赤銅色に日焼けした大佐は、誇らしい表情で目を輝かせた。
士気は高かったが俄か仕立ての反政府軍がカダフィの軍隊を破ったのは、NATOの強力な援護射撃があったからだ。当然見返りを要求される。
兵器体系が、これまでのロシア・中国製から欧米製となることは避けられない。米軍機が再び我が物顔でマイティガ基地を離着陸する日は、秒読み段階に入った。歴史は繰り返す。