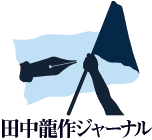アフガニスタンとパキスタンの国境沿いにまたがる部族地帯(トライバルエリア)は、南北約1,000km、東西50~200kmの細長い地域だ。人口は300万人余りと言われ(日本のように国勢調査があるわけではないので正確な数は不明)、ほとんどがパシュトゥン族である。
19世紀、ロシアは本国からインド洋への出口を求めて南下政策を進めており、英国はインド亜大陸を植民地とした後、さらなる領土拡張を目指していた。激突寸前となった両国は協定し、アフガニスタンを「手をつけない」緩衝地帯とした。
この後、英領インドとアフガニスタン政府は現在のパキスタン・アフガニスタン国境辺りを国境とする線引きをした。この国境線は、パシュトゥン族の居住地域を真っ二つに分断することになった。パシュトゥン族は分割を主導したイギリスに反発し、部族地帯は反英闘争の温床となった。英領インド政府はパシュトゥン懐柔策として「高度な自治」を与えた。
1947年、パキスタンはインドから分離独立した。インドとの厳しい軍事対立を抱えるパキスタンは東西に狭い。国防上、1kmでも奥行きがほしいパキスタンは、部族地帯はしっかり抱き込んでおく必要があった。こうして部族地帯の「高度な自治」は温存され、現在もパキスタン政府の警察権は及ばない。イスラム原理主義者の「聖地」として手つかずで残っっているのには、こうしたインド・パキスタン両国の思惑を受けた歴史的な事情がある。
パキスタン側から陸路でアフガニスタンに入るには、この部族地帯を通過しなければならない。難所のカイバル峠をやっと越えたかと思うと、そこは部族地帯だ。アフガニスタンに入るという「覚悟」を決めるには、もってこいの緊張感をもたらしてくれる。
ソ連のアフガニスタン侵攻(1979年~89年)の際は、「ここから続々、ムジャヒディーン(聖戦士)や兵器が供給されたんだ」。通訳を務めてくれたアフガニスタン国籍の青年は、言葉をかみしめるようにして語った。
屋外にいる男たちは当たり前のようにカラシニコフ自動小銃を肩にかけていた。だが物騒な雰囲気はない。想像していたような恐ろしさはなかった。南アジアの強烈な日差しが照りつけているのだが、生暖かく柔らかい風が頬をなでた。のどかで時間が止まったようだ。

部族地帯は現在ではかつてのムジャヒディーンに代わって、タリバンやアルカイーダの出撃拠点となっている。9・11テロの首謀者とされるビン・ラディンが潜伏しているとの報道も一時あった。
2004年、米ブッシュ政権にそそのかされたパキスタンのムシャラフ大統領が部族地帯に軍隊を踏み込ませたことがあった。その部隊は多大な犠牲者を出して進攻は失敗に終わった。ムシャラフ大統領はイスラム原理主義勢力の反発を買い、2度も暗殺未遂に遭った。
2度目は大統領の車列が通過した橋が爆破された。通過があと10数秒遅かったらムシャラフ大統領は車もろ共、河に転落していたところだった。「殺したい時はいつでも殺す」という強烈なメッセージだった。
パキスタンの軍部は、イスラム原理主義者が半分を占めているといわれる。英国領インドの一部だったパキスタンは、宗教上の理由からインドと袂を分かった歴史を持つ。しかも、そのインドと3次にわたって砲火を交じえた「印パ戦争」の歴史がある。
アフガニスタンに多大な影響を及ぼしているパキスタンは、軍事政権の国である。アフガン国境に近い古都ペシャワルには幹線道路にトーチカがある。鉄道は旅客列車よりも軍用列車の方が優先され、大砲や戦車など兵器を満載した列車が大地を行く。筆者はこれらの光景を見て、この国が戦時体制下にあることを痛感せざるを得なかった。
ヒンズー教の大国としてのインドへの対抗心を支えるのが、イスラム原理主義である。物理的な対抗力である軍部は、おのずと民衆のイスラム信仰を体現したものになる。彼らは「イスラムの兵士」との強い自覚を持つ。
パキスタン軍の諜報機関であるISI (Inter-Services Intelligence)は、「国家内国家」と言われるほど絶大な力を持つ。タリバンの誕生に深く関わったのがこの機関だ。
米国からタリバンへの資金援助とパキスタン軍からの軍事援助は、ISIを経由して行われたのだった。タリバンがアフガニスタンに現れた1994年頃はわずか兵力2,000人ほどだった。カブールを占拠した1996年には2万に増え、権力の絶頂にあった2000年には5万にまで膨れあがった。
タリバンの聖地とも言える部族地帯は、パキスタン軍部にとって「アンタッチャブル」なのである。ムシャラフ大統領は軍トップの参謀総長の身でありながら、部族地帯に軍を入れたのだった。それもイスラム原理主義勢力が最も嫌う米国ブッシュ政権のお先棒を担いでだ。重ねて暗殺を狙われたのも「当然の報い」ということになる。
パキスタンでは最高裁判所判事の更迭に端を発して昨秋から反ムシャラフ暴動が起きている。その中心にいるのが、部族地帯のイスラム原理主義勢力だ。タリバンやアルカイーダである。反ムシャラフ暴動は年を越しても大規模なまま続いている。
かりに米国がムシャラフ政権を切れば切ったで、部族地帯を目指すための橋頭堡を失う。パキスタンにあって軍人でありながらイスラム世俗主義を目指すムシャラフ大統領は、米国にとって実に操りやすい指導者だ。それでもパキスタン情勢は、米国の思惑通りには行っていない。
先日、暗殺されたブット元首相のような穏健派であれば、部族地帯はそっとしておくだろう。というより怖くて手をつけようなどとは思いもしないはずだ。
部族地帯はどんな政権だろうが「アンタッチャブル」だ。米国がどんなにけしかけようと、手を染めることは出来ない。
「ゲリラ戦に後背地は欠かせない」は、軍事のセオリーだ。そこで武器弾薬や食料を調達し、傷を癒やした兵士は再び戦列に復帰できる。タリバンやアルカイーダにとって部族地帯は格好の後背地となる。こうして、彼らが戦闘を持続できる構造が成り立っているのだ。《つづく》