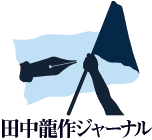アフガニスタンの各民族は地方に割拠して軍閥を形成している。その経済を支えてきたのが、ケシ栽培だ。高地で空気がよく乾燥しているため、純度の高いヘロインが精製される。当然、「世界市場」で人気が高い。アフガニスタンは、世界のケシ栽培量の実に92%を占める「ケシ王国」になってしまった。

タリバンや各地の軍閥はケシを売り、武器調達や民兵の給料に充てる。農民にとってもケシほど有難い「作物」はない。地元ジャーナリストによれば、普通の農作物の場合、1戸あたりの月収は100~200ドルだが、ケシは2,000~4,000ドルだ。普通の農作物の10倍~20倍にもなる。米軍はケシ撲滅にやっきとなっているが、タリバンや軍閥の前にはなす術もない。ケシ栽培農民にとってタリバンや軍閥は「守り神」のような存在だ。
国軍兵士の月収は6,000~8,000アフガニ(120~160ドル)。地元ジャーナリストによれば軍閥は倍の給料を出す。資金源はケシだ。「危ない目にあって給料が半分ではたまったものではない」。国軍の新兵が脱走して軍閥の民兵になるケースが多い、という。
カルザイ政権が発足して間もない頃、農業省の幹部は筆者に「内戦前は農業が国の富の半分を占めていた。農業がちゃんと復興すれば人々はケシ栽培に頼らなくて済む」と熱っぽく語ってくれた。ところが、農業の復興は容易ではなかった。畑を潤すカレーズ(農業用水路)が20年にわたる内戦で壊滅的な打撃を受けていたからだ。農地を人間の体にたとえるなら、カレーズは血管のように隅々にまで張り巡らされている。深さが2m位だったことからゲリラ戦の塹壕として使われた。
復旧作業が始まったばかりの2002年、筆者は現場を訪れた。形といい大きさといいマグロのような不発弾がゴロゴロと、カレーズから掘り出されていた。周りは一面ぶどう畑だった地域だ。だが、ぶどうの木はすっかり枯れていた。「こんなになっちゃって、どうしようもないじゃねえか」。農民は嘆きながらかたっぱしから倒していった。ぶどうの木は乾いた音を立てて根元から倒れた。

新しい苗木を植えても実をつけるまでは何年もかかる。政府や米軍が力づくで止めても、農民がケシ栽培に頼るのはひとえに生活のためだ。地球温暖化がこれに追い討ちをかけた。アフガニスタンではほとんど雨は降らない。大地に恵みの水をもたらすのは万年雪だ。それが温暖化でめっきり少なくなったのだ。
アフガニスタンの農業従事者は労働人口の8割をも占める。国の土台だ。それが今、崩壊の危機にさらされているのである。
米軍はソ連軍の二の舞となるか
生活をズタズタにした長い内戦が終ったと思ったら、異教徒の米軍がやってきて我が物顔でアラーの国を牛耳ろうとしている。敬虔なイスラム教徒であるアフガンの人々は、心穏やかであろうはずがない。
カブール郊外で村人に聞いた。
――カルザイ大統領をどう思うか?
「アメリカの従者なのでノーグッドだ」
――もしまた内戦になったらタリバンとカルザイ政権のどちらを支持するか?
「イスラム法を守っている方」
キリスト教文化の欧米諸国に支えられたカルザイ政権と、頑なにイスラム原理主義を貫くタリバン。どちらがイスラム法に則っているかは、改めていうまでもない。
カルザイ政権になってから、商店ではポルノのCDやDVDが売られるようになった。それらの店が保守的な人たちに襲われることもある。ビールも大きなホテルでは飲める。ポルノも酒も明らかにコーランの教えに反するものだ。
村人はタリバンを天敵としていたマスード派のムジャヒディーン(聖戦士)だった。それでも異教徒に操られたカルザイ政権よりタリバンを支持するというのだ。

ムジャヒディーンたちはイスラムを冒涜する者に対しては死を賭して戦う。戦乱の絶えない国で生まれ育った彼らにとって戦争は生活の一部だ。DNAに刻み込まれているといってよい。カラシニコフ自動小銃を畑のアゼに置き農耕にいそしみながら戦闘に出かける人々だ。
彼らは、今は不本意ながら米軍とカルザイ政権により武装解除されている。だが、ケシ栽培で軍資金は豊かだ。彼らに近代的な兵器が潤沢に渡るようなことになれば、米軍といえど窮地に追い込まれるだろう。撤退を余儀なくされた旧ソ連軍の二の舞を、今度は米軍が演ずる日が来ないとは限らない。《連載おわり》