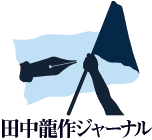ガザ市北東部のアルショハダ村は、ペタリとした平地だらけのガザにあって小高い丘の上に広がる。イスラエル国境までわずか1kmだ。坂を登りきり目に飛び込んできた村の景色に息を飲んだ。約1km四方にわたって家屋は一軒残らず破壊され、赤味を帯びた地肌がむき出しになっている。なぎ倒されたモスクの尖塔が、村に容赦ない爆撃が浴びせられたことを物語る。
アルショハーダ村の傍を通るアルカラーマ・ロードは、ガザを南北に貫く一大幹線道路のイラハディン・ロードと先でつながる。村は戦略要衝の地だ。「ハマス」と「イスラム聖戦」の部隊が村の外周に陣取り、侵攻してきたイスラエル軍と凄絶な戦闘を繰り広げた。村が徹底的に破壊されたのはこのためだ。
国際赤十字が贈ったテント50張りが整然と並ぶが、誰一人としてテント暮らしをする人はいない。ガザは今雨期で、朝夕は東京とあまり変わらない位冷え込む。「テントは雨と寒さで使い物にならない」と村人たちは話す。
鉄筋コンクリートの家屋は破壊されても大小の隙間ができる。村人たちは大きめの隙間で雨露をしのいでいる。無残に変わり果てた自分の家だが、テントと比べればはるかに暮らしやすい。
ムハマド・ズィアル・ハドゥルさん(47歳)の「お宅」を覗いた。10畳ほどのスペースに一家20人が寝起きする。暖を取るため夜中も交代で起き、薪の火を絶やさぬようにしている、という。筆者が訪ねた時、ハドゥルさんは雨水でコーヒーをたてていた。

ハドゥルさんにイスラエル軍が侵攻してきた時の状況を聞いた(以下ハドゥルさんの証言)――
1月14日に攻撃が始まった。最初に空爆があり、次に戦車が入ってきて砲撃された。家屋はさらにダイナマイトで爆破された。その後、ブルドーザーが残った家屋を潰し、畑の木々を根こそぎにした(空爆→戦車→ダイナマイト→ブルドーザーは、村人の誰に聞いても同じことを話した)。非戦闘員の村人40人が殺された。
攻撃は3日間続いた(「3日間」という日数も一致する)。ハドゥルさんは9人の子供を両手に抱き、瓦礫のすきまに身を潜め3日間やり過ごした。
「ここにはハマスもテロリストもいない。イスラエルこそテロリストだ」。ハドゥルさんは、筆者の質問には答えず繰り返し叫んだ。
こちらが止めなかったら、果てしなく同じフレーズを繰り返していただろう。自らも「精神に変調を来たしているものが多い」と語るが、話ぶりを聞いていて頷けた。侵攻時の経緯を聞き出すのに、筆者も同じ質問を幾度も繰り返さねばならず、かなりの時間と労力を要した。
妻のオムハドルさん(39歳)は「攻撃前はオリーブの木々もオレンジもレモンもあったが、今は砂漠だ」と吐き捨てた。
村人たちは苛酷な生活環境に置かれているのだが、国際赤十字の医師は週に一度しか来ない。深刻なのは、医師の診断で疾病が明らかになっても薬がないことだ。
別の一家の女性(40代)は「アブマーゼン(パレスチナ暫定自治政府アッバス大統領の別名)は何もしてくれない。着る服もない。食べ物もない」と絶叫する。女性は、息子を今回の戦闘で失っている。
「鶏、牛、ヤギも爆撃で殺された」「仕事も家もない」。村人(男性・30代)は訴えるように話す。すべてを失ったアルショハダ村に残っているのは絶望だけだった。