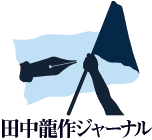島根県隠岐中ノ島の漁港・崎(さき)。漆黒の空にまだ星が輝く午前5時に定置網漁が始まる。冬ともなれば日本海を渡る風は身を切るように冷たい。作業船に乗組む漁師7人のうち5人は本土からの転職者だ。いわゆるIターンである。
網をすぼめるロープを手際よくたぐり寄せているのは、佐伯岳人さん(45才)だ。漁師になる前は横浜でガードマンをしていた。島に移り住んで4年が経つ。5年前(2005年)の夏、東京・池袋で開かれた「U・Iターンイベント」で島を知った。
佐伯さんは自身も両親も東京生まれ。田舎暮らしに憧れていた。その年の秋、初めて島を訪れると、想像していた通り自然がふんだんにあった。
眼前には青い海が広がり、後ろを振り向けば山が迫る。常緑樹と紅く染まった広葉樹のコントラストが目にしみた。磯の香りは都会人の鼻孔と心をツンと刺激した。「ここに住もう」。佐伯さんは即、決断。翌06年1月1日、妻と4人の子供と一緒に島にやってきた。
海の仕事は初めてだった佐伯さんは、船酔いにひどく悩まされた。佐伯さんをよく知る役場の職員によれば半年間吐き続けた、という。本人は「ひと月位ですよ」と笑う。
「最初の一年は無我夢中だった。漁労長に叱られても何を叱られているのかさえ分からなかった。一年経って何をやっているのかわかるようになった。仕事の段取り。どの時期にどの魚が獲れるか」。「漁師を始めたのが一月。寒さが一番つらかった」。懐かしそうに振り返る。
一年が経ち仕事にも自信がついた佐伯さんは、一戸建ての自宅を購入した。島に来た当時中学2年生だった長男はいま高校3年生だ。「定置網がある限り島に居続けますよ」。迷いのない明るい笑顔で語った。
伊藤健さん(46才)はIターン第一号だ。2005年10月、家族と共に島に移住してきた。40才を過ぎての転職である。それまでは大阪でホテルマンをしていた。島での漁師の仕事は妻がインターネットで見つけた。
もともと他人にペコペコするのが嫌いだった。ホテルの経営形態が財団法人から民間に変わり窮屈になったところで転職を決意した。
移り住むまでに島に3度来て漁師の実習を受けた。3回目は漁港そばの借家に一ヶ月間滞在しながら船に乗った。「やろう。これしかない」。伊藤さんは島で漁師になることを決断した。
「体はエライけど昼頃仕事が終わる。明るいうちから一杯やれる(飲める)からいい」と屈託ない。「島で漁師になって良かったと思う時は?」と聞くと「家から海が見える時。自然と共に生きるのがいい」とニッコリ笑った。
島にダイビングに来ているうちにすっかり島に魅せられて漁師に転職した若者もいる。丹野裕貴さん(26才)だ。丹野さんは仙台でコンピューターのシステム・エンジニアをしていたが、「転職するなら早い方がいい」と強く思うようになった。島に来てからちょうど1年が経った。
筆者は漁船に同乗したが、誰が根っからの漁師で誰がIターンなのか、区別がつかない。魚網をたぐる手も揺れる船上での身のこなしも皆同じように見えた。
都会の生活に疲れた人々を家族ぐるみで島に引きつけるために行政はどんな努力をしているのか。Iターンで島に来た人たちが地域の活性化のどう役立っているのか。連載で報告する。
(つづく)