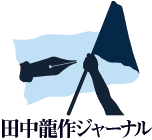アフガニスタンの復興支援をめぐっては、「PRT( Provincial Reconstruction Team=地域復興チーム)への自衛隊派遣」案が、与野党共にある。民主党は「国連安保理決議があれば自衛隊を派遣する」とし、自民党は「決議がなくても派遣できる恒久法」の制定を目指している。

「PRTは武力行使を伴わない」などと言うと聞こえはいいが、実態はISAF(アイサーフ=国際治安支援部隊)の1部隊である。
PRTは軍事的には宣撫工作にあたる部門だ。宣撫とは、占領地住民に占領政策を理解させて民心を安定させることをいう。誤爆や乱射で反感を買った分、学校を建設したり、医薬品を提供したりして現地人を懐柔するのである。ところが、かえって地元住民の反感を買っているのがPRTの現状だ。
とりわけ米軍のPRTは嫌われている。ナンガルハル州では2005年3月、米軍のPRTがやってきて数種類の薬をバラ撒いた。使用方法など一切示さずにだ。おまけに射撃訓練までしていった、という。
実際、部隊配置としてもPRTは、アフガニスタン全土(東・西・南・北の4地域)に展開するISAF4個師団の下に置かれる。ISAFを指揮するのはNATO(北大西洋条約機構)で、現在のISAF司令官は米軍のマクネイル将軍である。これだけ見ても、アフガンが「アメリカの戦争」であることが分かる。
日本のNGOは医療支援や農業支援など地道な活動で地元に貢献している。中村哲医師が率いる「ペシャワール会」はその代表的な例だ。
それが、「日本人というだけで、アフガニスタンの人々から温かく受け入れられていた。だが、インド洋上での給油継続問題がアフガニスタンのメディアでも取り上げられると、白い目で見られるようになった」。ある日本人NGOスタッフが残念そうに語った。
日本が米国の同盟国であることは地元の人もよく知っている。日本が自衛隊を派遣すれば、復興支援といえどもアメリカと同一視され、テロの標的にされる危険性は十分にある。

いったん兵を退いただけのタリバン
筆者が前回、アフガニスタンを訪れたのは2002年だった。ISAF発足直後だ。ロヤジルガ(民族大会議)が開かれ、カルザイ氏が大統領に就任、閣僚も決まった。日本や欧米のメディアは「新生アフガニスタンの夜明け」などとする趣旨の報道に染まった。
カブール市内は夜でも1人歩きできるほど治安が良好だった。筆者は「フルシチョフ型住宅」と呼ばれるアパートに宿泊していて、毎晩のようにホテルまでインターネットを利用しに出かけた。ところが、今では外国人の1人歩きは日中でも危険と言われる。誘拐や爆弾テロに遭う危険があるからだ。1人だけの夜間外出などはもう、自殺行為に等しい。
その時の取材では、パキスタンのペシャワールから部族地帯を通り、アフガニスタンの東都・ジャララバードを抜けて首都カブールに入った。舗装されている道はほんの一部。荒れ放題のラフロードが、内戦の長さと酷さを感じさせた。
今ではこのルートは海外のゼネコンによりすっかり舗装されている。だが通行するには武装したコンボイ(護衛隊列)を組み、「スラヤ」(直接通信衛星に電波を打ち上げる大ぶりの携帯電話)を持たねばならない、と言われている。
アフガニスタンのほぼ全土で治安は悪化していることは間違いないようだ。原因の1つはDDR(Disarmament, Demobilization, Reintegration=武装解除・動員解除・社会復帰)が計画倒れに終ったことだ。2003年に始まったDDRのために日本は資金全体の4分の3にあたる9,100万ドル(約160億円)もを拠出した。
現地でDDRに携わったある日本政府関係者は「DDRの最大の過ちは、タリバンを武装解除しなかった(できなかった)ことだ」とくちびるを噛む。2001年11月、米軍と北部同盟がカブールを陥れた時、メディアは「戦勝報道」に沸いた。
ところが、タリバンは撃滅され敗退したわけではなかった。部族地帯(トライバルエリア)やパキスタンにいったん兵を退いただけだ。もちろん兵器は携えたままで、戦術の一環である。筆者は2002年にペシャワールで「つい先日までタリバン兵だった」いう青年に会った。青年の兄は部族地帯の方にいる、と涼しい顔で話した。
アフガニスタンとパキスタンの国境にまたがる部族地帯は「地理上」ではパキスタン領だが、実際にはパキスタン政府の警察権も行政権も及ばない。アフガニスタン紛争の鍵を握るのが、この部族地帯だ。《つづく》